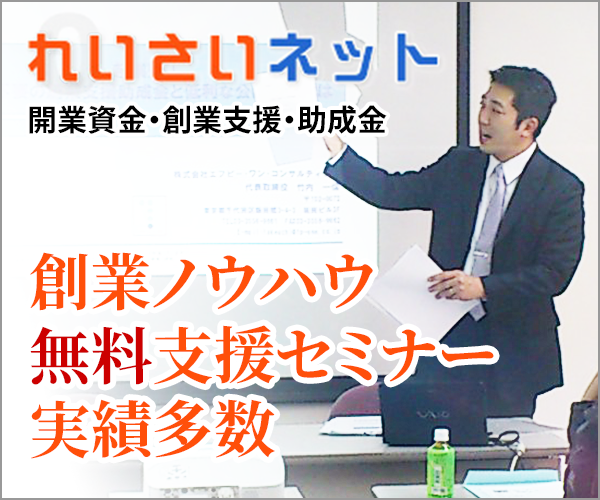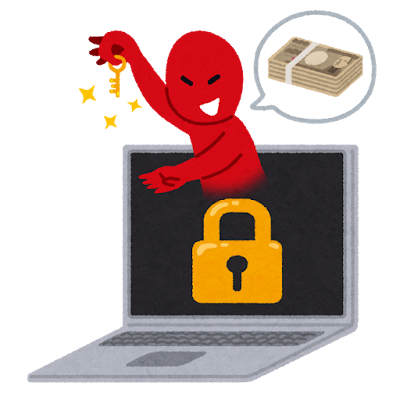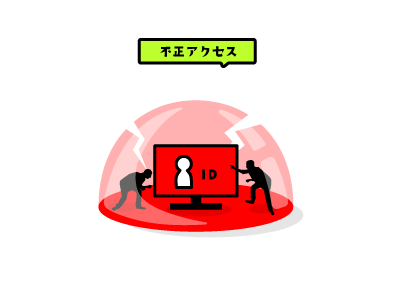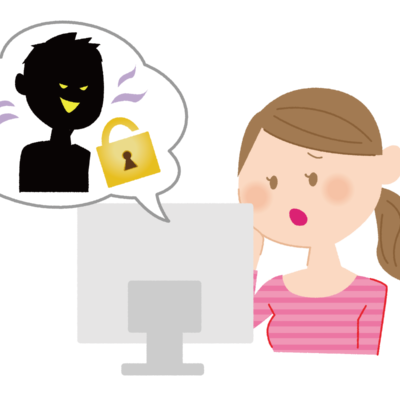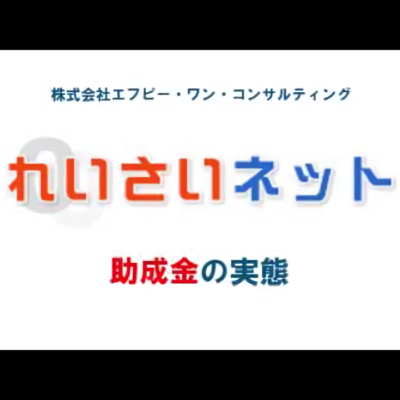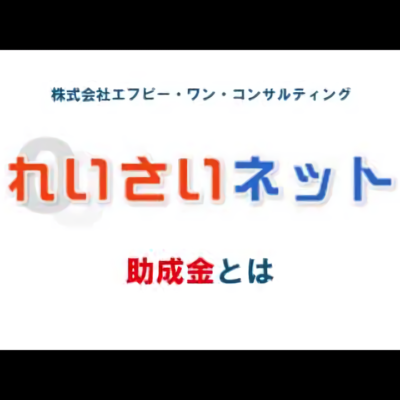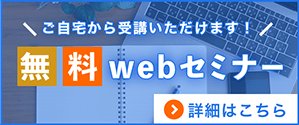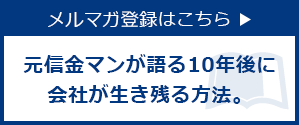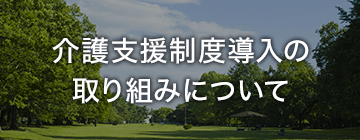『AI活用と情報漏洩リスク~企業と個人が取るべき対応策~』
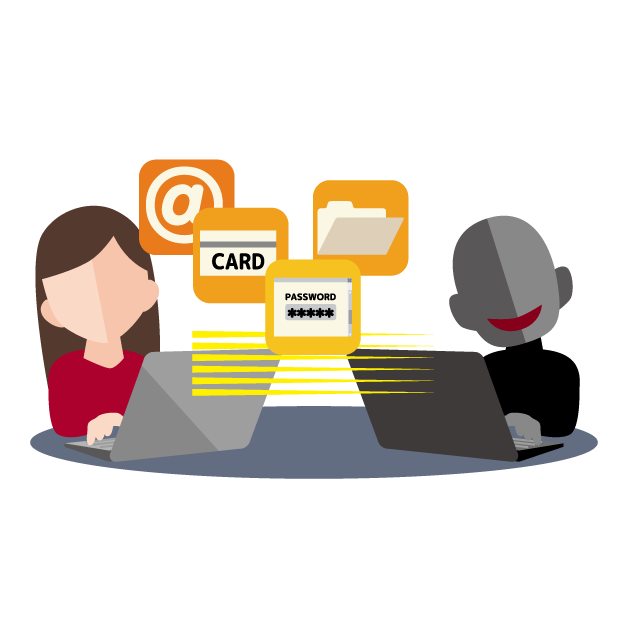
近年生成AIの急速な普及に伴い、企業や個人が業務効率化やクリエイティブな作業に活用するケースが増えています。しかしその一方で、AIの利用に伴う情報漏洩リスクが懸念されています。特にAIが入力データを学習し、機密情報が第三者に流出する可能性が指摘されており、中国の新興企業DeepSeekに関する報道もその一例です。本記事ではAIを活用する際の情報漏洩リスクと、企業や個人が取るべき対応策について解説します。
1. AI活用における情報漏洩のリスクとは?
生成AIや大規模言語モデル(LLM)は、ユーザーが入力したデータを処理して回答を生成します。しかし、以下のようなリスクが存在します。
① 入力データの再利用・学習による漏洩
一部のAIは、ユーザーが入力した情報を学習し、他のユーザーの回答に反映させることがあります。機密情報や個人情報をAIに入力すると、意図せずに第三者へ開示されるリスクがあるのです。
② AIプロバイダーのデータ管理体制の問題
AIを提供する企業がサーバーにデータを保存し、適切なセキュリティ対策を講じていなければ、不正アクセスやデータ漏洩が発生する可能性があります。
③ AIの誤出力による情報流出
AIが誤って過去の学習データを出力し、意図しない情報が開示されるケースもあります。特に、企業が内部文書を入力してAIを活用する際には要注意です。
2. 企業や個人が取るべき対応策
AIの活用は便利ですが、情報漏洩のリスクを抑えるために、企業や個人は以下の対策を講じるべきです。
企業向けの対応策
① AI利用ポリシーの策定
• 社内でAIを利用する際のルールを明確化し、機密情報の入力を禁止する。
• 利用するAIツールを事前に精査し、データ管理ポリシーを確認する。
② 社員向けの情報セキュリティ教育
• AIのリスクについて社員に周知し、適切な利用方法を教育する。
• 具体的な事例を交えて、どのような情報をAIに入力すべきでないかを理解させる。
③ セキュアなAIサービスの選定
• データを学習しないオプションがあるAIツールを選ぶ(例:企業向けのカスタムAI)。
• 社内でAIモデルを開発・運用し、機密情報を外部に送らない仕組みを構築する。
個人向けの対応策
① 機密情報の入力を避ける
• 住所、電話番号、パスワード、機密文書などはAIに入力しない。
• 仕事で使用する場合は、会社のルールに従い、情報の取り扱いに注意する。
② AIツールの利用規約を確認する
• AIが入力データをどのように処理するのかを確認し、必要ならばデータ削除の手続きも検討する。
• 無料ツールよりも、セキュリティ対策が強化された有料版の利用を検討する。
③ 二次情報の取り扱いにも注意
• AIの出力結果をそのまま他者に共有するのではなく、内容を精査する。
• AIが誤った情報を生成する可能性があるため、必ず裏付けを取る。
3. これからのAI活用と情報管理の重要性
生成AIの進化により、業務効率化やクリエイティブな活用が進む一方で、情報漏洩リスクも高まっています。企業や個人が適切な対応を取ることで、AIの利便性を享受しながら安全に活用することが可能です。
AI時代においては、「利便性」と「セキュリティ」のバランスが求められます。今後、企業や政府による規制強化も進む可能性があるため、最新の動向を把握しながら、適切なAI活用を心がけることが重要です。
安全なAI活用を意識し、賢く使いこなしましょう!